コラム
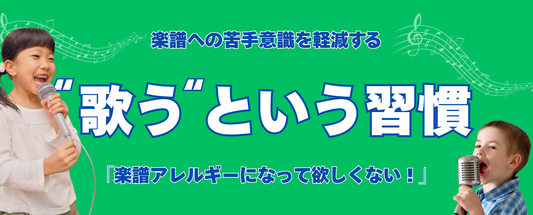
「楽譜アレルギーになって欲しくない!」楽譜への苦手意識を軽減する「歌う」という習慣
「この黒いオタマジャクシ、暗号にしか見えない…」 かつてピアノのレッスンで、分厚い楽譜集を前に、そう絶望したことはありませんか?あるいは、合唱の授業で、自分だけ楽譜のどこを歌っているのか分からず、必死に隣の子の口元を見て歌を合わせた、なんていう苦い思い出は。 そして今、お子さんが楽しそうに楽器に触れていたり、歌を口ずさんでいたりする姿を見て、ふとよぎる不安。 「この子には、自分と同じように楽譜でつまずいて、音楽を嫌いになってほしくない」「でも、楽譜の読み方をどう教えたらいいか分からないし、無理強いして音楽そのものが嫌いになったら元も子もない…」 その気持ち、痛いほどよく分かります。 楽譜が読めなくても、音楽を楽しむことはできます。しかし、もし楽譜という「音楽の世界地図」を読み解くことができたら、お子さんの音楽の世界は、豊かに、そしてどこまでも広がっていくはずです。 実は、楽譜を「読み解く力」は、難しい訓練や生まれつきの才能がなくても、お家での”ある遊び”を習慣にするだけで自然に身につけることができるのです。 この記事では、かつて楽譜に挫折した親御さんだからこそ、お子さんにプレゼントできる「楽譜と仲良くなるための、全く新しいアプローチ」をご紹介します。それは、楽器も難しい理論も必要ない、「歌うだけ」というとてもシンプルな習慣です。 ...
「楽譜アレルギーになって欲しくない!」楽譜への苦手意識を軽減する「歌う」という習慣
「この黒いオタマジャクシ、暗号にしか見えない…」 かつてピアノのレッスンで、分厚い楽譜集を前に、そう絶望したことはありませんか?あるいは、合唱の授業で、自分だけ楽譜のどこを歌っているのか分からず、必死に隣の子の口元を見て歌を合わせた、なんていう苦い思い出は。 そして今、お子さんが楽しそうに楽器に触れていたり、歌を口ずさんでいたりする姿を見て、ふとよぎる不安。 「この子には、自分と同じように楽譜でつまずいて、音楽を嫌いになってほしくない」「でも、楽譜の読み方をどう教えたらいいか分からないし、無理強いして音楽そのものが嫌いになったら元も子もない…」 その気持ち、痛いほどよく分かります。 楽譜が読めなくても、音楽を楽しむことはできます。しかし、もし楽譜という「音楽の世界地図」を読み解くことができたら、お子さんの音楽の世界は、豊かに、そしてどこまでも広がっていくはずです。 実は、楽譜を「読み解く力」は、難しい訓練や生まれつきの才能がなくても、お家での”ある遊び”を習慣にするだけで自然に身につけることができるのです。 この記事では、かつて楽譜に挫折した親御さんだからこそ、お子さんにプレゼントできる「楽譜と仲良くなるための、全く新しいアプローチ」をご紹介します。それは、楽器も難しい理論も必要ない、「歌うだけ」というとてもシンプルな習慣です。 ...
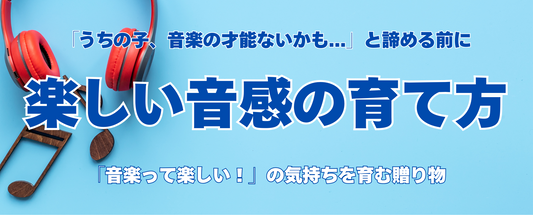
「うちの子、音楽の才能ないかも…」と諦める前に。音楽に挫折した親が、わが子に贈る「楽しい音感の...
「昔、ピアノを習っていたけど、練習が嫌でやめてしまった…」「楽しそうに歌っているけど、ちょっと音が外れているかも…これって音痴なのかな?」 お子さんの将来を想うからこそ、音楽との関わり方について、こんな風に悩んだことはありませんか? 特に、ご自身が過去に楽器の練習でつまずいたり、音楽の授業が苦手だったりした経験があると、「わが子には、音楽で豊かな人生を送ってほしい」と願う気持ちと、「でも、自分と同じように苦労させてしまったらどうしよう」という不安との間で、心が揺れ動いてしまうのではないでしょうか。 ただ純粋に音楽を楽しんでほしいだけなのに、無理やり音楽教室に通わせるのは気が引ける。かといって、自分は音楽に詳しくないし、家で何をしてあげたら良いか分からない…。 でも、もう大丈夫です。 もし、お家で「勉強」や「練習」としてではなく、親子で夢中になって「遊んでいる」うちに、自然と音楽を聴き分ける”耳”が育っていくとしたら、試してみたいと思いませんか? 実は、ピアノの前に座る必要も、難しい楽譜の知識もいらない。ソファに座りながら、絵本を読むように音楽に触れられる。そんな嬉しい方法があるんです。 この記事では、かつて音楽に挫折してしまった親御さんだからこそ、お子さんにプレゼントできる「新しい音楽との出会い方」をご紹介します。読み終える頃には、「才能なんて関係なかったんだ!」と、きっと心が軽くなっているはずです。 --- Ratatone®も、小学生のお子様へのプレゼント、小学校入学前(3歳から5歳)のプレゼント用に購入されています。お子様の興味の幅を拡げたい、楽しく音楽に触れてほしいという方に最適です! ▼Ratatone®公式サイト▼楽器に触れる前に音や音楽に触れる。 ...
「うちの子、音楽の才能ないかも…」と諦める前に。音楽に挫折した親が、わが子に贈る「楽しい音感の...
「昔、ピアノを習っていたけど、練習が嫌でやめてしまった…」「楽しそうに歌っているけど、ちょっと音が外れているかも…これって音痴なのかな?」 お子さんの将来を想うからこそ、音楽との関わり方について、こんな風に悩んだことはありませんか? 特に、ご自身が過去に楽器の練習でつまずいたり、音楽の授業が苦手だったりした経験があると、「わが子には、音楽で豊かな人生を送ってほしい」と願う気持ちと、「でも、自分と同じように苦労させてしまったらどうしよう」という不安との間で、心が揺れ動いてしまうのではないでしょうか。 ただ純粋に音楽を楽しんでほしいだけなのに、無理やり音楽教室に通わせるのは気が引ける。かといって、自分は音楽に詳しくないし、家で何をしてあげたら良いか分からない…。 でも、もう大丈夫です。 もし、お家で「勉強」や「練習」としてではなく、親子で夢中になって「遊んでいる」うちに、自然と音楽を聴き分ける”耳”が育っていくとしたら、試してみたいと思いませんか? 実は、ピアノの前に座る必要も、難しい楽譜の知識もいらない。ソファに座りながら、絵本を読むように音楽に触れられる。そんな嬉しい方法があるんです。 この記事では、かつて音楽に挫折してしまった親御さんだからこそ、お子さんにプレゼントできる「新しい音楽との出会い方」をご紹介します。読み終える頃には、「才能なんて関係なかったんだ!」と、きっと心が軽くなっているはずです。 --- Ratatone®も、小学生のお子様へのプレゼント、小学校入学前(3歳から5歳)のプレゼント用に購入されています。お子様の興味の幅を拡げたい、楽しく音楽に触れてほしいという方に最適です! ▼Ratatone®公式サイト▼楽器に触れる前に音や音楽に触れる。 ...
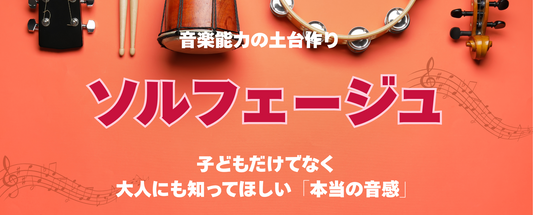
音楽能力の土台作り「ソルフェージュ」 - 子どもだけでなく大人にも知ってほしい「本当の音感」
「ソルフェージュ?言葉は聞いたことあるけどよく分からない!?」 「うちの子、吹奏楽部だけど、もっと音楽を深く理解できたら、演奏も変わるのかな?」 音楽教育にお子様を関わらせる保護者の方や、部活動で楽器に打ち込む学生の皆さんなら、一度はそんな風に思ったことがあるかもしれません。 練習は裏切らない、とは言われますが、ただ楽譜通りに指を動かすだけ、正しい音を出すだけの作業になってしまうと、音楽が持つ本来の楽しさや感動は見失われがちです。 その鍵を握るのが、音楽教育の土台と言われる「ソルフェージュ」。 この言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、その本当の目的や、現代の教育が抱える課題までご存知の方は少ないかもしれません。この記事では、ソルフェージュとは何か、その光と影、そしてこれからの時代に求められる「本当の音感」の育て方について、深く掘り下げていきます。 --- Ratatone®も、小学生のお子様へのプレゼント、小学校入学前(3歳、4歳、5歳)のプレゼント用に購入されています。お子様の興味の幅を拡げたい、楽しく音楽に触れてほしいという方に最適です! ▼Ratatone®公式サイト▼楽器に触れる前に音や音楽に触れる。 感受性を刺激する幼少期のお子様のプレゼントとして最適な知育楽器Ratatone®の購入ページはこちら --- 音楽能力の土台作り「ソルフェージュ」とは? ...
音楽能力の土台作り「ソルフェージュ」 - 子どもだけでなく大人にも知ってほしい「本当の音感」
「ソルフェージュ?言葉は聞いたことあるけどよく分からない!?」 「うちの子、吹奏楽部だけど、もっと音楽を深く理解できたら、演奏も変わるのかな?」 音楽教育にお子様を関わらせる保護者の方や、部活動で楽器に打ち込む学生の皆さんなら、一度はそんな風に思ったことがあるかもしれません。 練習は裏切らない、とは言われますが、ただ楽譜通りに指を動かすだけ、正しい音を出すだけの作業になってしまうと、音楽が持つ本来の楽しさや感動は見失われがちです。 その鍵を握るのが、音楽教育の土台と言われる「ソルフェージュ」。 この言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、その本当の目的や、現代の教育が抱える課題までご存知の方は少ないかもしれません。この記事では、ソルフェージュとは何か、その光と影、そしてこれからの時代に求められる「本当の音感」の育て方について、深く掘り下げていきます。 --- Ratatone®も、小学生のお子様へのプレゼント、小学校入学前(3歳、4歳、5歳)のプレゼント用に購入されています。お子様の興味の幅を拡げたい、楽しく音楽に触れてほしいという方に最適です! ▼Ratatone®公式サイト▼楽器に触れる前に音や音楽に触れる。 感受性を刺激する幼少期のお子様のプレゼントとして最適な知育楽器Ratatone®の購入ページはこちら --- 音楽能力の土台作り「ソルフェージュ」とは? ...
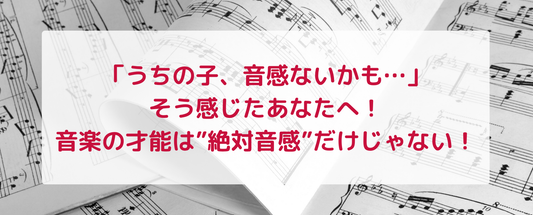
「うちの子、音感ないかも…」そう感じたあなたへ!音楽の才能は”絶対音感”だけじゃない!
こんにちは。Ratatone®担当のTJです。これまでのRatatone®プロジェクトで得た学びや気づき、音楽を楽しく遊ぶための研究、そして私たちが新たに開発している音に特化したカードゲームについて報告していきたいと思います。 --- 現在、私たちはRatatone®の新たな形として、音で遊ぶカードゲームを開発中です!Makuake、CAMPFIRE、GREENFUNDING、Kibidangoなど、いろんなクラウドファンディングのプラットフォームを比較し、最適な発表のタイミングを探っています。詳細はブログとSNSでお知らせ予定です! --- 誕生日の特別な贈り物に。女の子が夢中になる音楽プレゼント「ラタトーン」がおすすめ! ▼前回の活動報告はこちら▼【2025年7月活動報告②】音楽が"特別"じゃない家庭でも、"耳"が自然と育つように。「音のカードゲーム」に込めた想いを全て語ります! 音楽の才能は”絶対音感”だけじゃない! 「絶対音感」という言葉を聞いて、「あれは特別な才能だから、自分や自分の子供には縁のない世界だ」と、どこかで線を引いてしまっていませんか? かつてピアノのレッスンで苦労した経験から、「自分には音楽の才能がない」と思い込んでしまった親御さん。お子さんには音楽で豊かな人生を歩んでほしいと願いつつも、「うちの子も自分に似て、飽きっぽいし、才能なんてないかも…」と、一歩を踏み出せずにいるあなたへ。 もし、音楽の入り口が、もっと楽しく、もっと自由で、まるでゲームのように夢中になれるものだとしたら、どうでしょう? 「絶対音感」がなくたっていい! ...
「うちの子、音感ないかも…」そう感じたあなたへ!音楽の才能は”絶対音感”だけじゃない!
こんにちは。Ratatone®担当のTJです。これまでのRatatone®プロジェクトで得た学びや気づき、音楽を楽しく遊ぶための研究、そして私たちが新たに開発している音に特化したカードゲームについて報告していきたいと思います。 --- 現在、私たちはRatatone®の新たな形として、音で遊ぶカードゲームを開発中です!Makuake、CAMPFIRE、GREENFUNDING、Kibidangoなど、いろんなクラウドファンディングのプラットフォームを比較し、最適な発表のタイミングを探っています。詳細はブログとSNSでお知らせ予定です! --- 誕生日の特別な贈り物に。女の子が夢中になる音楽プレゼント「ラタトーン」がおすすめ! ▼前回の活動報告はこちら▼【2025年7月活動報告②】音楽が"特別"じゃない家庭でも、"耳"が自然と育つように。「音のカードゲーム」に込めた想いを全て語ります! 音楽の才能は”絶対音感”だけじゃない! 「絶対音感」という言葉を聞いて、「あれは特別な才能だから、自分や自分の子供には縁のない世界だ」と、どこかで線を引いてしまっていませんか? かつてピアノのレッスンで苦労した経験から、「自分には音楽の才能がない」と思い込んでしまった親御さん。お子さんには音楽で豊かな人生を歩んでほしいと願いつつも、「うちの子も自分に似て、飽きっぽいし、才能なんてないかも…」と、一歩を踏み出せずにいるあなたへ。 もし、音楽の入り口が、もっと楽しく、もっと自由で、まるでゲームのように夢中になれるものだとしたら、どうでしょう? 「絶対音感」がなくたっていい! ...
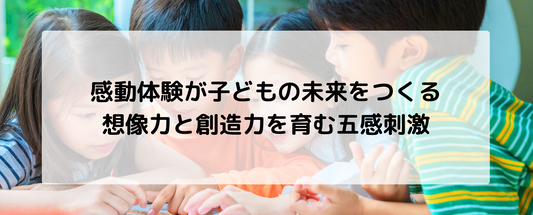
感動体験が子どもの未来をつくる—想像力と創造力を育む五感刺激
私たちは日々の暮らしの中で、映画や絵画、音楽、自然や人のふるまいに触れて「感動体験」を味わっています。この「感動」は、直感的に心が動かされる場合もあれば、過去の経験や知識、文脈的理解をもとに生まれることもあります。 幼少期の感動体験は、自己肯定感、自己効力感、知的好奇心やチャレンジ精神を高めることにつながると言われています。しかし、まだ体験も経験も未熟で、知識も文脈も持たない純粋無垢な子どもたちにとって、「感動」はどのようにして起きるのでしょうか?そしてそれは、大人が経験する感動とどのように違うのでしょうか? 本記事では、子どもにとっての「感動」がどのようなものかを、「原初的な感動」というキーワードを軸に掘り下げていきます。 ▼Ratatone®公式サイト▼ 創造力を育むラタトーン パズルのような知育おもちゃや、絵本とは異なった考え方から生まれた聴覚から創造力を育む知育楽器Ratatone® 感動とは「心が動くこと」 「感動」は、「感(かんじる)」+「動(うごく)」で構成される言葉です。つまり、感動とは本質的に「心が揺れ動く体験」と考えられます。 大人にとっての感動は、意味づけや価値判断、知識や経験による理解といったものが影響します。一方、子ども、特に未就学児においては、物語の背景や構造、象徴的意味などは理解していない場合がほとんどです。 では、彼らは感動できないのでしょうか? 答えは「いいえ」です。 むしろ、彼らの感じる感動は、私たち大人が忘れかけている純粋な感情のゆらぎ=原初的な感動であるとも言えるのです。 子どもの五感が揺さぶられる原初的な感動体験 赤ちゃんが風にふかれて笑う。小さな子どもが、初めて聴いた音楽に合わせて体を揺らす。キラキラした光に目を見開いてじっと見つめる。 これらの反応は、すべて「知識」や「意味づけ」を伴わない、感覚的で直接的な情動反応です。この段階の感動には、次のような特徴があります。 五感による刺激(音、色、光、触感など)への反応 安心、不安、喜び、驚きといった基本的な情動 意味を理解していなくても起こる心の動き つまり、これは「新しい発見や体験」をきっかけにして心が反応している状態ではあるものの、 大人のように「なぜそれが新しいのか」「それに何の意味があるのか」といった意味づけを経ていません。「知らなかったことを知る」「初めての体験をする」ことがトリガーとなり、子どもたちの心が大きく揺れる。これが、子どもにおける「原初的な感動」の本質です。 感動の発達段階と心の成長 感動は、成長とともに少しずつ変化し、複雑になっていきます。 感覚的感動(0〜3歳) 音、光、触感、色などの感覚刺激に対して、無意識に心が動く。 「理由なき感動」の段階。 情緒的感動(3〜6歳) 簡単な物語への共感、他人の表情や行動に感情を重ねるようになる。...
感動体験が子どもの未来をつくる—想像力と創造力を育む五感刺激
私たちは日々の暮らしの中で、映画や絵画、音楽、自然や人のふるまいに触れて「感動体験」を味わっています。この「感動」は、直感的に心が動かされる場合もあれば、過去の経験や知識、文脈的理解をもとに生まれることもあります。 幼少期の感動体験は、自己肯定感、自己効力感、知的好奇心やチャレンジ精神を高めることにつながると言われています。しかし、まだ体験も経験も未熟で、知識も文脈も持たない純粋無垢な子どもたちにとって、「感動」はどのようにして起きるのでしょうか?そしてそれは、大人が経験する感動とどのように違うのでしょうか? 本記事では、子どもにとっての「感動」がどのようなものかを、「原初的な感動」というキーワードを軸に掘り下げていきます。 ▼Ratatone®公式サイト▼ 創造力を育むラタトーン パズルのような知育おもちゃや、絵本とは異なった考え方から生まれた聴覚から創造力を育む知育楽器Ratatone® 感動とは「心が動くこと」 「感動」は、「感(かんじる)」+「動(うごく)」で構成される言葉です。つまり、感動とは本質的に「心が揺れ動く体験」と考えられます。 大人にとっての感動は、意味づけや価値判断、知識や経験による理解といったものが影響します。一方、子ども、特に未就学児においては、物語の背景や構造、象徴的意味などは理解していない場合がほとんどです。 では、彼らは感動できないのでしょうか? 答えは「いいえ」です。 むしろ、彼らの感じる感動は、私たち大人が忘れかけている純粋な感情のゆらぎ=原初的な感動であるとも言えるのです。 子どもの五感が揺さぶられる原初的な感動体験 赤ちゃんが風にふかれて笑う。小さな子どもが、初めて聴いた音楽に合わせて体を揺らす。キラキラした光に目を見開いてじっと見つめる。 これらの反応は、すべて「知識」や「意味づけ」を伴わない、感覚的で直接的な情動反応です。この段階の感動には、次のような特徴があります。 五感による刺激(音、色、光、触感など)への反応 安心、不安、喜び、驚きといった基本的な情動 意味を理解していなくても起こる心の動き つまり、これは「新しい発見や体験」をきっかけにして心が反応している状態ではあるものの、 大人のように「なぜそれが新しいのか」「それに何の意味があるのか」といった意味づけを経ていません。「知らなかったことを知る」「初めての体験をする」ことがトリガーとなり、子どもたちの心が大きく揺れる。これが、子どもにおける「原初的な感動」の本質です。 感動の発達段階と心の成長 感動は、成長とともに少しずつ変化し、複雑になっていきます。 感覚的感動(0〜3歳) 音、光、触感、色などの感覚刺激に対して、無意識に心が動く。 「理由なき感動」の段階。 情緒的感動(3〜6歳) 簡単な物語への共感、他人の表情や行動に感情を重ねるようになる。...
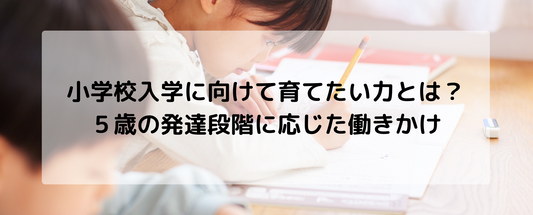
小学校入学に向けて育てたい力とは?5歳の発達段階に応じた働きかけ
小学校入学を控えた5歳児のこの時期 この時期の発達は、身体、認知、社会性、言語、感情と多方面にわたり、将来の学習や対人関係に直結する大切な土台となります。親としては「うちの子、大丈夫かな?」という不安を感じることも少なくないでしょう。しかし、発達段階の特徴と、それに応じた働きかけを知ることで、安心して子どもと向き合うことができます。 今回は、5歳児の発達段階の特徴から小学校入学前に育みたい能力、そしてそれらの能力をバランス良く育む音楽遊びについてご紹介します。 ▼Ratatone®公式サイト▼ 聴く力を育むラタトーン パズルのような知育おもちゃや、絵本とは異なった考え方から生まれた聴覚から創造力を育む知育楽器Ratatone® 5歳児の発達段階の特徴 身体的な発達に加え、知的・言語的・社会的な側面でも著しい伸びが見られます。自立心や主体性が育つ一方で、反抗的な態度や友達とのトラブルも増えますが、これらは成長の一過程です。多様な経験と適切な関わりを通じて、子どもの発達を支えていくことが重要です。 身体的発達:バランスと器用さの向上 5歳児は筋力や体力が向上し、平均台を渡る、スキップをする、リボン結びなど手先の器用さも発達します。五感への感覚刺激を積極的に取り入れることで、体の使い方がよりスムーズになり、運動能力の向上にもつながります。 認知・知的発達:理解力と論理的思考の芽生え 数字や文字、時間、曜日や大小関係などの概念を理解できるようになります。なぜ?どうして?という疑問から探求心が育ちます。小学校の学習に必要な学習能力はこの時期から芽生えはじめます。 言語とコミュニケーション能力:会話力の発達 「どうして〇〇なの?」という質問が多くなり、大人と対等な会話ができるようになる子も。自分の思いや考えを言葉で伝える力が伸び、対人関係に必要な土台を築きます。 社会性と感情の発達:ルールと協調性の理解 友達と遊びのルールを決めたり、意見のぶつかり合いから折り合いをつけたりと、協調性や思いやりが育ちます。一方で反抗期的な振る舞いも見られ、自立心の発達とともに、自己主張が強まります。 ▼Ratatone®公式サイト▼ 聴く力を育むラタトーン パズルのような知育おもちゃや、絵本とは異なった考え方から生まれた聴覚から創造力を育む知育楽器Ratatone® 小学校入学に向けて育てたい力 小学校に入学すると「学習」が始まりますが、先生の話をしっかり聞けるのか、学校の授業についていけるのか、といった不安は誰もが感じていると思います。確かに、読み・書き・そろばんといった勉強の先取り教育も重要ですが、それよりも重要なのは「能力向上のための土台作り」です。 聴く力と集中力:学びの基盤 学習能力を高めるために欠かせないのが「聴く力」です。音や言葉をただ耳に入れるだけでなく、意味を理解しようとする能動的な聴き方が、創造力や論理的思考を育て、対人関係の形成にもつながります。 自分で考え行動する力:自律性の基礎 5歳は、自分のことを自分でやりたがる時期です。モンテッソーリ教育でも強調されているように、自ら選び、自ら行動する中で主体性と自律心が育ちます。小学校生活では、自分で準備をしたり、スケジュールを把握したりする力が求められるため、この時期からの積み重ねが重要です。 対人関係スキル:社会生活の土台 友達とのトラブルやルールに沿ったコミュニケーションなど、社会の中で自分を表現しながらも、相手と協調する力が必要になります。音楽合奏遊びや運動などを通して「自分」と「相手」を意識する経験は、コミュニケーションの土台を養います。 感覚刺激による学び:五感を使った体験 音や色、手触り、匂いなど五感に働きかける体験は、記憶や理解を助け、感受性や創造力の土台となります。特に音楽遊びは、リズム感、表現力、協調性、創造力をバランスよく育てる優れた方法です。 聴く力、集中力、自律性、対人スキルなど、小学校入学前に育みたい力は様々ありますが、一体どんな遊びや学びを取り入れれば育むことができるのでしょうか。実は、それらの能力を効率的にバランスよく育むことができる遊びがあります。...
小学校入学に向けて育てたい力とは?5歳の発達段階に応じた働きかけ
小学校入学を控えた5歳児のこの時期 この時期の発達は、身体、認知、社会性、言語、感情と多方面にわたり、将来の学習や対人関係に直結する大切な土台となります。親としては「うちの子、大丈夫かな?」という不安を感じることも少なくないでしょう。しかし、発達段階の特徴と、それに応じた働きかけを知ることで、安心して子どもと向き合うことができます。 今回は、5歳児の発達段階の特徴から小学校入学前に育みたい能力、そしてそれらの能力をバランス良く育む音楽遊びについてご紹介します。 ▼Ratatone®公式サイト▼ 聴く力を育むラタトーン パズルのような知育おもちゃや、絵本とは異なった考え方から生まれた聴覚から創造力を育む知育楽器Ratatone® 5歳児の発達段階の特徴 身体的な発達に加え、知的・言語的・社会的な側面でも著しい伸びが見られます。自立心や主体性が育つ一方で、反抗的な態度や友達とのトラブルも増えますが、これらは成長の一過程です。多様な経験と適切な関わりを通じて、子どもの発達を支えていくことが重要です。 身体的発達:バランスと器用さの向上 5歳児は筋力や体力が向上し、平均台を渡る、スキップをする、リボン結びなど手先の器用さも発達します。五感への感覚刺激を積極的に取り入れることで、体の使い方がよりスムーズになり、運動能力の向上にもつながります。 認知・知的発達:理解力と論理的思考の芽生え 数字や文字、時間、曜日や大小関係などの概念を理解できるようになります。なぜ?どうして?という疑問から探求心が育ちます。小学校の学習に必要な学習能力はこの時期から芽生えはじめます。 言語とコミュニケーション能力:会話力の発達 「どうして〇〇なの?」という質問が多くなり、大人と対等な会話ができるようになる子も。自分の思いや考えを言葉で伝える力が伸び、対人関係に必要な土台を築きます。 社会性と感情の発達:ルールと協調性の理解 友達と遊びのルールを決めたり、意見のぶつかり合いから折り合いをつけたりと、協調性や思いやりが育ちます。一方で反抗期的な振る舞いも見られ、自立心の発達とともに、自己主張が強まります。 ▼Ratatone®公式サイト▼ 聴く力を育むラタトーン パズルのような知育おもちゃや、絵本とは異なった考え方から生まれた聴覚から創造力を育む知育楽器Ratatone® 小学校入学に向けて育てたい力 小学校に入学すると「学習」が始まりますが、先生の話をしっかり聞けるのか、学校の授業についていけるのか、といった不安は誰もが感じていると思います。確かに、読み・書き・そろばんといった勉強の先取り教育も重要ですが、それよりも重要なのは「能力向上のための土台作り」です。 聴く力と集中力:学びの基盤 学習能力を高めるために欠かせないのが「聴く力」です。音や言葉をただ耳に入れるだけでなく、意味を理解しようとする能動的な聴き方が、創造力や論理的思考を育て、対人関係の形成にもつながります。 自分で考え行動する力:自律性の基礎 5歳は、自分のことを自分でやりたがる時期です。モンテッソーリ教育でも強調されているように、自ら選び、自ら行動する中で主体性と自律心が育ちます。小学校生活では、自分で準備をしたり、スケジュールを把握したりする力が求められるため、この時期からの積み重ねが重要です。 対人関係スキル:社会生活の土台 友達とのトラブルやルールに沿ったコミュニケーションなど、社会の中で自分を表現しながらも、相手と協調する力が必要になります。音楽合奏遊びや運動などを通して「自分」と「相手」を意識する経験は、コミュニケーションの土台を養います。 感覚刺激による学び:五感を使った体験 音や色、手触り、匂いなど五感に働きかける体験は、記憶や理解を助け、感受性や創造力の土台となります。特に音楽遊びは、リズム感、表現力、協調性、創造力をバランスよく育てる優れた方法です。 聴く力、集中力、自律性、対人スキルなど、小学校入学前に育みたい力は様々ありますが、一体どんな遊びや学びを取り入れれば育むことができるのでしょうか。実は、それらの能力を効率的にバランスよく育むことができる遊びがあります。...
